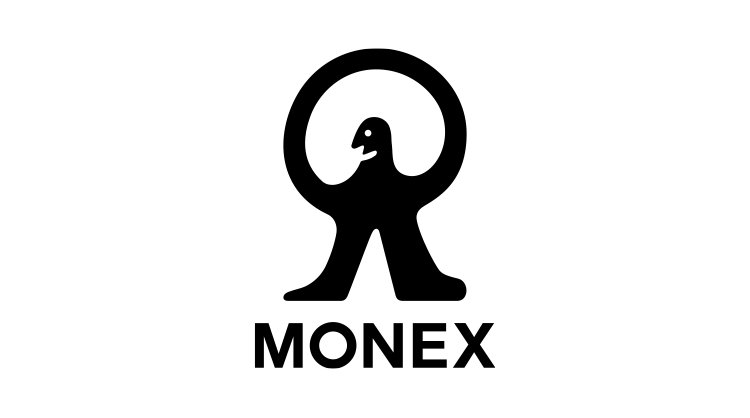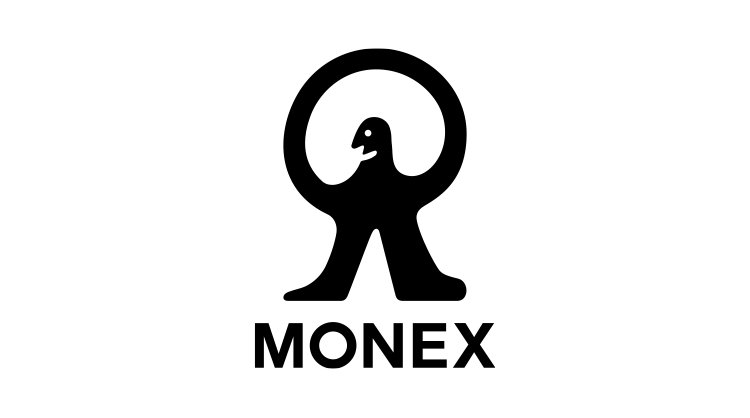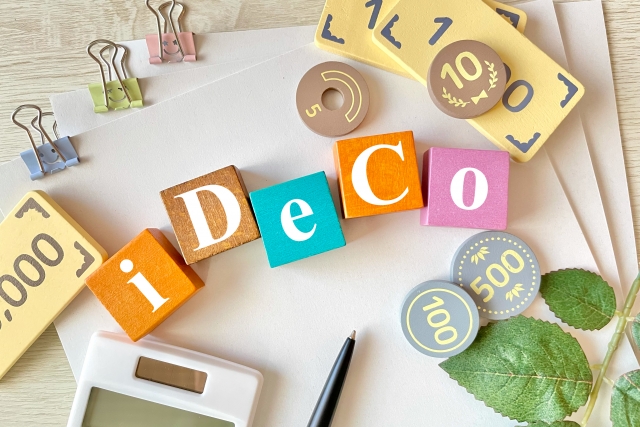受取りはやっぱり60歳以上にならないとできないのかな?
と疑問に思われた方。
 うーさん
うーさん答えは原則Yes!
ですが、2つ例外がありますので一部NO!です。
また、iDeCoは受け取る時に課税をされます。
非課税と国が宣伝していますが、受取り時には課税されますので騙されたような…?
しかし、国もその辺はちゃんと考えていますので、どのように受け取ればお得になるのかを書いてます。
3つの給付金と3つの受け取り方
原則は60歳以上からの給付ですが、あまり知られていませんが例外があります。
- 障害給付金(60歳前でも引き出し可能)
- 死亡一時金(60歳前でも引き出し可能)
- 老齢給付金(原則60歳以降)
- 年金‥5~20年の間で『均等額で取り崩し』『均等割合で取り崩し』など選ぶことができます。
- 一時金‥一括でお金を引き出すことをいいます。
- 併給‥『年金』と『一時金』の組み合わせの事をいいます。
障害給付金(60歳前でも引き出し可能)


病気やケガなどで障害を抱えてしまったときに引き出せるお金。
- iDeCoを掛けている人が高度障害になった場合
- ・障害基礎年金(1~2級)を受け取っている
・身体障害者手帳(1~3級)の交付を受けた
・療養手帳(重度)の交付を受けた
・精神障碍者保健福祉手帳(1~2級)の交付を受けた
※高度障害の場合引出し可能
- 受け取り方
- ・年金、一時金、併用どれで受け取っても全額非課税
死亡一時金(60歳前でも引き出し可能)
加入している本人が亡くなった時に遺族が受け取れるお金。
- iDeCoを掛けている人が死亡したした場合に請求できる人
- ・配偶者
・子
・両親
・孫
・祖父母
・兄弟姉妹
※遺族が自分で請求しないともらえないので注意!!!
- 受け取り方
- ・一時金のみ。
500万円×法定相続人の数=全額非課税
※iDeCo加入者が亡くなってから3年以内に請求しなければ非課税枠が使用不可となるので注意!!
老齢給付金
原則60~75歳の自分の好きな時に受け取れるお金。(2022年4月以降は60~70歳)
ただし加入期間が10年未満の場合、受け取れる年齢が後ろ倒しになるので注意が必要です。
受け取り方は3パターンあります。
年金として受けとる場合
年金として受け取る場合は雑所得扱いになります。
公的年金控除が使えますが、気をつけなかければいけないのが非課税枠です。
◎65歳未満‥年額60万円まで非課税
◎65歳以上‥年額110万円まで非課税
国民年金は年間受取り満額約80万円なので、iDeCoからの受取りを30万円以下にすれば全額非課税で受け取ることができますね。
一時金として受け取る場合
一時金として受け取る場合は退職金所得控除が使えます。
退職金がない自営業者や、退職金が少ない会社員におすすめです。
計算方法は下記の通り。
★勤続20年以下の場合
加入年数×40万円=退職所得控除額
↓
(退職金-退職所得控除)×1/2=課税所得金額
↓
課税される
★勤続20年超の場合
800万円+(勤続年数-20年)×70万円=退職所得控除額
↓
(退職金-退職所得控除)×1/2=課税所得金額
↓
課税される
併給として受け取る場合
雑所得+退職所得の二つの枠を使うことが出来ます。
iDeCoの残高が多めの人などにおススメ。
企業から退職金を受け取る場合
iDeCoで退職所得控除を使えて、定年退職時にも退職所得控除を使えるってこと?!
2回も使えるって最高じゃん!
と思う方がいるかもしれません。
実は一定期間をあければ退職所得控除を使うことは可能です。
iDeCoと退職所得の両方に退職所得控除を使う方法は下記の通りです。
- iDeCoと退職所得の両方に退職所得控除を使う方法
- ①勤務先→退職金受け取る
iDeCo→20年以上後に一時金を受け取る
②iDeCo→一時金受け取る
勤務先→5年以上後に退職金を受け取る
手数料
年金として受け取る場合、口座管理料や給付手数料等がかかります。
給付事務手数料として440円/回とお高め。
一時金で受け取る方は1度のみ支払えば終わりですが、年金受け取りの方でしたら年6回×10年とすると、60回。
60回×440円=26,400円!!
とかなり高額になるので、一時金受取りの方がお得なのではないかと思います。
60歳以降も運用する方は、引出しをせずにそのままiDeCo口座で運用した方が良いですね。
チェックポイント
iDeCoは差し押さえ禁止財産ですので、倒産したり借金があったとしてもiDeCoがなくなることはありません。※国税の滞納による差し押さえを除く。